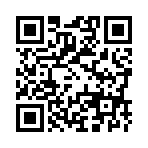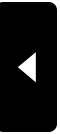2010年11月12日
2010房総アジング総括②
アジングでの常夜灯の効果について。
今まで一番顕著だった例で、隣にカゴアジ師がいてその方は少し沖目のブレイクライン狙い。
かなり沖なので常夜灯の灯りの影響は全く無いと言っていいと思います。
しかもそのカゴ師、全くもって灯り云々を意識してる様子もありません。(そりゃそうか・・・?^^;)
私は手前の浅場の常夜灯の灯りが届く範囲&それより少し遠目を攻めてました。
カゴ師は仕掛けの都合上、当然手前の浅場(1〜2m弱程度)は狙えませんので必然的にそうなります。
最初、カゴのコマセに足止めされて手前の浅場にはアジが入って来ないだろうな〜と半ば諦めてました。
しかし、そんな状況でもヤツラ級の良型が釣れたんです。 今改めて検証してみると・・・
実はそのカゴ師の方、何度も同じ場所で同じ状況でご一緒してるんです。
お話した事は一度もありませんが・・・^^;
そしてパターンとしては、お互いポツポツ拾ってたり、どちらか一方がポツポツ釣ってるのにもう一方は
沈黙してたり、双方沈黙だったり・・・まあ、どれをとっても爆釣という事はありませんでしたが;^^;;
元々があまり大きな群れが回遊してくるような場所でもないと思うので、こういう形になったのかも。
で、それこそ正にアジの臨機応変なのではなかろうか・・・と。
前回記事に通じる事なんですが、同じ場所に回遊してくるアジの群れは毎回同じとも限りませんが
少なくとも釣り上げたアジの全てが金色の体色だったので、やはり近海定着型のアジかと。
で、上記の結果によりその時々によって、また、違う群れによって、更には群れの中でも個々に・・・
明らかに食事の対象を選り好みしてる様子が見て取れます。
何故かは・・・アジが人間の言葉で返答してくれれば越した事はないのですが(渇望笑)
とにかくここで言えるのは、コマセや付け餌に好反応な時もあれば、手前の常夜灯の灯りに寄った
ベイト類を食いたい時もある=アジングで釣れる=餌釣りにも勝る常夜灯の威力は確かに存在する、と。
もしこんなシチュエーションがあったら、諦めずに攻めてみるのも手ではないかと。
次に、常夜灯の色調について。
大部分を占めるのは白色灯・オレンジ灯・白熱球の三種類だと思います。
個人的にはオレンジ灯と白熱球が良い釣果を得られてます。白色灯の場合、アジが居るには居るん
だけど他の二つの色調の灯りよりも食いがシブい印象を受けるのは、気のせいでしょうか?
オレンジ灯&白熱球の灯りは白色灯より暗めで、更に明暗の境が曖昧な部分が多いような印象・・・
これは視力の良いアジからすればベイトから身を隠しつつも目視して狙える&逆に小さなベイトの視力
ではアジが見えにくいという、アジにとっては有利な捕食ゾーンが広く取れる、という事になるのでは。
あと、良型アジについては色調を問わず海面を照らす灯りが明る過ぎる場所は釣れる気配がしません。
活性の高い時はかなり明るい足元まで追ってきてヒットした事もありましたが・・・
どちらかというと、常夜灯自体の光量があまりなく全体的に薄暗く海面を照らしてる感じか、
常夜灯の光源自体はそれなりに強くても立地条件等含め海面を照らす光量自体がボンヤリした感じの
場所なら、かなり岸際にも寄ってくるような印象を受けます。
これはあくまで私個人の経験による感覚なので、参考程度に考えて下さい。
最後に、月が明るい夜の場合。
これは前回釣行時、夜にも関わらず良型アジがイワシ?等の小さなベイトを追って小規模ですが
目の前で何回かナブラが起こったのを目撃しました。
夜間に良型アジが小魚を追ってナブラを起こす・・・という事は、やはり普段よりは月灯りで周囲も
ある程度見えていて、且つベイトを追う事が出来る視界が得られているという事に他ならないかと。
その場所には常夜灯はあるにはあったんですが、正直その光量と月の光量では常夜灯効果はまるで
無効どころか月灯りが勝ってる勢いでした。これは逆に、アジが回遊して来そうで且つベイトを
追い詰めるのに好都合なポイントを押さえていれば、月灯りの夜でも常夜灯に頼らずこういった
シーンに遭遇する確率が高くなり、アジングが成立するのでは、と。
以前からそういったポイントを開拓したく考えてはいるんですが、やはり上記のような理由でついつい
釣れる場所に行ってしまい、まだまだ実地検分が足りない状態です。
新たに購入したリールがそんなようなネーミングなので、そのままに・・・とか。^^;
今まで一番顕著だった例で、隣にカゴアジ師がいてその方は少し沖目のブレイクライン狙い。
かなり沖なので常夜灯の灯りの影響は全く無いと言っていいと思います。
しかもそのカゴ師、全くもって灯り云々を意識してる様子もありません。(そりゃそうか・・・?^^;)
私は手前の浅場の常夜灯の灯りが届く範囲&それより少し遠目を攻めてました。
カゴ師は仕掛けの都合上、当然手前の浅場(1〜2m弱程度)は狙えませんので必然的にそうなります。
最初、カゴのコマセに足止めされて手前の浅場にはアジが入って来ないだろうな〜と半ば諦めてました。
しかし、そんな状況でもヤツラ級の良型が釣れたんです。 今改めて検証してみると・・・
実はそのカゴ師の方、何度も同じ場所で同じ状況でご一緒してるんです。
お話した事は一度もありませんが・・・^^;
そしてパターンとしては、お互いポツポツ拾ってたり、どちらか一方がポツポツ釣ってるのにもう一方は
沈黙してたり、双方沈黙だったり・・・まあ、どれをとっても爆釣という事はありませんでしたが;^^;;
元々があまり大きな群れが回遊してくるような場所でもないと思うので、こういう形になったのかも。
で、それこそ正にアジの臨機応変なのではなかろうか・・・と。
前回記事に通じる事なんですが、同じ場所に回遊してくるアジの群れは毎回同じとも限りませんが
少なくとも釣り上げたアジの全てが金色の体色だったので、やはり近海定着型のアジかと。
で、上記の結果によりその時々によって、また、違う群れによって、更には群れの中でも個々に・・・
明らかに食事の対象を選り好みしてる様子が見て取れます。
何故かは・・・アジが人間の言葉で返答してくれれば越した事はないのですが(渇望笑)
とにかくここで言えるのは、コマセや付け餌に好反応な時もあれば、手前の常夜灯の灯りに寄った
ベイト類を食いたい時もある=アジングで釣れる=餌釣りにも勝る常夜灯の威力は確かに存在する、と。
もしこんなシチュエーションがあったら、諦めずに攻めてみるのも手ではないかと。
次に、常夜灯の色調について。
大部分を占めるのは白色灯・オレンジ灯・白熱球の三種類だと思います。
個人的にはオレンジ灯と白熱球が良い釣果を得られてます。白色灯の場合、アジが居るには居るん
だけど他の二つの色調の灯りよりも食いがシブい印象を受けるのは、気のせいでしょうか?
オレンジ灯&白熱球の灯りは白色灯より暗めで、更に明暗の境が曖昧な部分が多いような印象・・・
これは視力の良いアジからすればベイトから身を隠しつつも目視して狙える&逆に小さなベイトの視力
ではアジが見えにくいという、アジにとっては有利な捕食ゾーンが広く取れる、という事になるのでは。
あと、良型アジについては色調を問わず海面を照らす灯りが明る過ぎる場所は釣れる気配がしません。
活性の高い時はかなり明るい足元まで追ってきてヒットした事もありましたが・・・
どちらかというと、常夜灯自体の光量があまりなく全体的に薄暗く海面を照らしてる感じか、
常夜灯の光源自体はそれなりに強くても立地条件等含め海面を照らす光量自体がボンヤリした感じの
場所なら、かなり岸際にも寄ってくるような印象を受けます。
これはあくまで私個人の経験による感覚なので、参考程度に考えて下さい。
最後に、月が明るい夜の場合。
これは前回釣行時、夜にも関わらず良型アジがイワシ?等の小さなベイトを追って小規模ですが
目の前で何回かナブラが起こったのを目撃しました。
夜間に良型アジが小魚を追ってナブラを起こす・・・という事は、やはり普段よりは月灯りで周囲も
ある程度見えていて、且つベイトを追う事が出来る視界が得られているという事に他ならないかと。
その場所には常夜灯はあるにはあったんですが、正直その光量と月の光量では常夜灯効果はまるで
無効どころか月灯りが勝ってる勢いでした。これは逆に、アジが回遊して来そうで且つベイトを
追い詰めるのに好都合なポイントを押さえていれば、月灯りの夜でも常夜灯に頼らずこういった
シーンに遭遇する確率が高くなり、アジングが成立するのでは、と。
以前からそういったポイントを開拓したく考えてはいるんですが、やはり上記のような理由でついつい
釣れる場所に行ってしまい、まだまだ実地検分が足りない状態です。
新たに購入したリールがそんなようなネーミングなので、そのままに・・・とか。^^;
Posted by はるきち at 02:55│Comments(4)
│アジング考察
この記事へのコメント
おひさです。
そうなんです!
何がそうなのかといえば、
総括1・2のほとんどについて、そうなんです!
と共感いたしました。
大物ほど繊細…
どんな釣りでもこのような決め付け記事をよく目にしますが、
ヒネクレ者の私は、
そんな記事には商業的な背景を勘ぐってしまいます^^;
1ozメタルジグのアシスト2本両方に良型が掛かったりしますからね。繊細に攻めなきゃダメな時もありますけど。
そうなんです!
定着型のルートには既に常夜灯が含まれているのでしょうが、それ以外の餌場や、そこまでのルートを掴めれば…!
月明かりには私も可能性を感じていますし、真っ暗闇の中でも餌を食っているとも考えています。
縦アクションが効くとされる鯵は外洋回遊型ではないかと。
外から入ってきたばかりのワカシやカンパには、縦アクションが効きますし。
そして、中・小型の鯵。
つまりは、
魚側のスレ・見切り・警戒心が関係してるんじゃないでしょうか?
と思いました。
まぁ、長くなりましたが
単にアジング行きたいだけです(笑)
はるきちさんは今頃
房総かなぁ…
そうなんです!
何がそうなのかといえば、
総括1・2のほとんどについて、そうなんです!
と共感いたしました。
大物ほど繊細…
どんな釣りでもこのような決め付け記事をよく目にしますが、
ヒネクレ者の私は、
そんな記事には商業的な背景を勘ぐってしまいます^^;
1ozメタルジグのアシスト2本両方に良型が掛かったりしますからね。繊細に攻めなきゃダメな時もありますけど。
そうなんです!
定着型のルートには既に常夜灯が含まれているのでしょうが、それ以外の餌場や、そこまでのルートを掴めれば…!
月明かりには私も可能性を感じていますし、真っ暗闇の中でも餌を食っているとも考えています。
縦アクションが効くとされる鯵は外洋回遊型ではないかと。
外から入ってきたばかりのワカシやカンパには、縦アクションが効きますし。
そして、中・小型の鯵。
つまりは、
魚側のスレ・見切り・警戒心が関係してるんじゃないでしょうか?
と思いました。
まぁ、長くなりましたが
単にアジング行きたいだけです(笑)
はるきちさんは今頃
房総かなぁ…
Posted by fantastic at 2010年11月13日 11:21
・・・と思わせて実は居宅です(不可笑)
大物は確かに繊細な時もあるとは思うんですが、しかし。
房総の場合、陸っぱりアジングだと多くは浅場が舞台ですよね。
そもそもそんな浅場に入って来るアジはよもや食う気全開で入って
来てる訳です。そこへ私達がタイミング良く現場に入ってドスっと!
ヤツラ級のワームの追い方を何回か目視できたんですが、
結構な遠くからワーム目掛けて一直線にビューっと追い掛けてきて、
全く躊躇せず咥えた所で動きが止まり、そこでドスっとくる・・・んです。
繊細な釣りが好きな方には始めはエキサイティングでも釣れ方が単調
なので慣れてくると物足りなく思えてくるかもしれません。
しかし私はそのたまにしかないドスっと感触と、ヤツラ級とのライトタックル
ファイトに病み付いたカラダなので・・・(染笑)
・・・私的には、縦アクションが効くアジも房総では近海定着型かと。
で、近海定着型と言っても勿論回遊はしますが、その回遊の範囲も
割と岸寄りの浅い海域で尚且つ例えば外房なら外房のあまり広くない
外房の範疇の海域を往復したりしてるイメージなんですが・・・。
まあ、捉え方ではそれも外洋回遊型とも言えるかもしれませんが、
私の感覚ではあくまでもそれも房総地着きアジの範疇だと思うんですよ。
小型~大型まで実際見るあの体色は・・・同じ性質の種類のアジかと。
その上での捕食対象による臨機応変なのかな・・・?と。
私的には外洋回遊型アジというのはもっと岸から遠くて水深200m以上
ありそうな海域を全国的に回遊してるようなアジというのをイメージしてます。
本格的に船釣りで狙うような、体色の黒っぽいアジ・・・。
というか、私も房総釣査檄行きたいです(歯軋笑)
大物は確かに繊細な時もあるとは思うんですが、しかし。
房総の場合、陸っぱりアジングだと多くは浅場が舞台ですよね。
そもそもそんな浅場に入って来るアジはよもや食う気全開で入って
来てる訳です。そこへ私達がタイミング良く現場に入ってドスっと!
ヤツラ級のワームの追い方を何回か目視できたんですが、
結構な遠くからワーム目掛けて一直線にビューっと追い掛けてきて、
全く躊躇せず咥えた所で動きが止まり、そこでドスっとくる・・・んです。
繊細な釣りが好きな方には始めはエキサイティングでも釣れ方が単調
なので慣れてくると物足りなく思えてくるかもしれません。
しかし私はそのたまにしかないドスっと感触と、ヤツラ級とのライトタックル
ファイトに病み付いたカラダなので・・・(染笑)
・・・私的には、縦アクションが効くアジも房総では近海定着型かと。
で、近海定着型と言っても勿論回遊はしますが、その回遊の範囲も
割と岸寄りの浅い海域で尚且つ例えば外房なら外房のあまり広くない
外房の範疇の海域を往復したりしてるイメージなんですが・・・。
まあ、捉え方ではそれも外洋回遊型とも言えるかもしれませんが、
私の感覚ではあくまでもそれも房総地着きアジの範疇だと思うんですよ。
小型~大型まで実際見るあの体色は・・・同じ性質の種類のアジかと。
その上での捕食対象による臨機応変なのかな・・・?と。
私的には外洋回遊型アジというのはもっと岸から遠くて水深200m以上
ありそうな海域を全国的に回遊してるようなアジというのをイメージしてます。
本格的に船釣りで狙うような、体色の黒っぽいアジ・・・。
というか、私も房総釣査檄行きたいです(歯軋笑)
Posted by はるきち at 2010年11月13日 21:05
こんばんわ。
月明りでもベイトを追い詰める場所・・・うんうん。
確かに、メッキでも、夕マズメポイントはそんな感じですねぇ。
アジは満月だと散るっていいますが、どうなんでしょ。
アオリだと浮くので良いっていうのと、一致しない気もするんですが・・・。
月明りでもベイトを追い詰める場所・・・うんうん。
確かに、メッキでも、夕マズメポイントはそんな感じですねぇ。
アジは満月だと散るっていいますが、どうなんでしょ。
アオリだと浮くので良いっていうのと、一致しない気もするんですが・・・。
Posted by TAT at 2010年11月17日 20:20
at 2010年11月17日 20:20
 at 2010年11月17日 20:20
at 2010年11月17日 20:20アジは満月だと散るというのは、あくまで常夜灯の明かりに寄って来た
アジを対象に釣りをしてる釣り人側の一方的都合による結果論であって、
アジからすればベイトを捕食するのに都合が良いのは夜間でも
見えるという事が肝心だと思うんですよ。
アジは基本昼行性とはいいますが、そこはやはり野生の生き物、
常夜灯に限らず夜間でも視界が得られれば餌を食う・・・
前回の現場での事実がそれを証明してると思います。
しかしそれなら尚更ポイントが拡がり過ぎて狙い所を絞り辛くなる・・・でも。
考えてみれば、アジが回遊してきそうな場所や餌場は灯り関連を
抜かしてもある程度は絞られると思います。それは、昼間にもアジングで
デイアジが成立する事と意味合い的には同じ事だと思うんですよ。
アオリは満月だと浮くので良い
=アオリのベイトとなるアジもベイトを追って浮き気味になってる
=アオリもアジを狙って浮いてくる
=アオリが浮いてきたのでアジは散る。
こういう事ですかね・・・。
アジを対象に釣りをしてる釣り人側の一方的都合による結果論であって、
アジからすればベイトを捕食するのに都合が良いのは夜間でも
見えるという事が肝心だと思うんですよ。
アジは基本昼行性とはいいますが、そこはやはり野生の生き物、
常夜灯に限らず夜間でも視界が得られれば餌を食う・・・
前回の現場での事実がそれを証明してると思います。
しかしそれなら尚更ポイントが拡がり過ぎて狙い所を絞り辛くなる・・・でも。
考えてみれば、アジが回遊してきそうな場所や餌場は灯り関連を
抜かしてもある程度は絞られると思います。それは、昼間にもアジングで
デイアジが成立する事と意味合い的には同じ事だと思うんですよ。
アオリは満月だと浮くので良い
=アオリのベイトとなるアジもベイトを追って浮き気味になってる
=アオリもアジを狙って浮いてくる
=アオリが浮いてきたのでアジは散る。
こういう事ですかね・・・。
Posted by はるきち at 2010年11月21日 01:13
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。