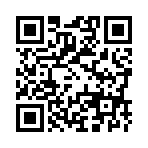2010年11月25日
ヤエン綺羅キャロ
以前からキャロについて、もっと簡単に現場でリグれないものかと思ってました。
スプリットの方が簡単なんですが、どうも私は感覚的にキャロの方が好みみたいで・・・
単純に好みとかだけでイイのか? とは思うんですが、そこは・・・まあ^^;
例えば最初はジグヘッド単体で投げてて、急遽遠目のポイントを探りたくなった時。 その逆も然り。
基本をジグヘッド単体として考えて、このような時にワンタッチで装着できれば・・・と。

ヤエンからヒントを得て作ってみました。 ツノは単なる願望です(弓笑)

試作壱号。見ての通りなんですが、端の辺りで絡みが頻繁に発生しそう&厄介になりそうな構造・・・
柔かいFIXパイプなのでたわみが出て剛性面で少々・・・両端をライターで溶かして密閉してるので
その部分だけでも多少浮力が得られる構造になってはいますが。

試作弐号。ジェットテンビンのステンワイヤーを流用しました。浮き素材を通してから適当な長さに
調整して両端をリング状に加工。ラインを切らずにワンタッチ装着できます。
また、ガン玉のウエイトを変えて自由に重量調整できます。


弐号が実用に耐えうるかもしれません。これも糸絡みが気になりますが、両端のリング形状の部分を
少々吟味してみたのであとは実釣あるのみです。 嫌な予感も多々ありますが・・・;^^;;
スプリットの方が簡単なんですが、どうも私は感覚的にキャロの方が好みみたいで・・・
単純に好みとかだけでイイのか? とは思うんですが、そこは・・・まあ^^;
例えば最初はジグヘッド単体で投げてて、急遽遠目のポイントを探りたくなった時。 その逆も然り。
基本をジグヘッド単体として考えて、このような時にワンタッチで装着できれば・・・と。

ヤエンからヒントを得て作ってみました。 ツノは単なる願望です(弓笑)

試作壱号。見ての通りなんですが、端の辺りで絡みが頻繁に発生しそう&厄介になりそうな構造・・・
柔かいFIXパイプなのでたわみが出て剛性面で少々・・・両端をライターで溶かして密閉してるので
その部分だけでも多少浮力が得られる構造になってはいますが。

試作弐号。ジェットテンビンのステンワイヤーを流用しました。浮き素材を通してから適当な長さに
調整して両端をリング状に加工。ラインを切らずにワンタッチ装着できます。
また、ガン玉のウエイトを変えて自由に重量調整できます。


弐号が実用に耐えうるかもしれません。これも糸絡みが気になりますが、両端のリング形状の部分を
少々吟味してみたのであとは実釣あるのみです。 嫌な予感も多々ありますが・・・;^^;;
2010年11月18日
2010房総アジング総括③
良型アジが釣れた時のみに焦点を絞って、日時・潮汐を調べてみました。
1/23 19:30 小潮 上げ5分
5/1 21:00 中潮 下げ4~5分
5/3 2:30 中潮 上げ3~5分
5/5 19:30 小潮 上げ6~7分
6/13 1:00 大潮 上げ2~3分
10/11 3:30 中潮 上げ2~5分
10/11 19:30 中潮 下げ2~3分
10/16 21:00 小潮 ほぼ満潮
10/23 23:15 大潮 ほぼ干潮
房総釣査に年間通して通ってみたのは、今回のようなデータを出してみて釣れる確率の高い時の条件が
何か絞られてくるのでは? と思っていたのですが・・・正直、日時・潮汐ともバラバラでした。
傾向としては諸般の定説通り潮が動いている時間帯で尚且つ上げ潮時が最も釣果が高い・・・ですが。
満潮干潮時のあまり潮の動きが感じられないような時間帯でも釣れてます。いや、むしろ・・・
これもあくまで私個人的経験による感覚になってしまいますが、満潮時よりもド干潮時、もしくは
その前後の潮位が低い時間帯の方が釣果が良いように感じてます。 推測なんですが、その場所に
アジが入ってきて捕食を繰り返してる間、釣り人が誰も入らず場荒れも無くアジが警戒心を解いて
ある程度長い時間その場所に留まっている・・・特に房総は元から水深が浅いので、人的プレッシャー
さえ無ければ尚更水深が浅くなる場所が捕食には好都合な訳で・・・。
ここでもう一度データを見返しつつ各釣行を思い返してみると、確かに大潮の満潮時とかのフル水位の
ような時は釣果が無く、またアジが釣れる気配も希薄だったような気がします。
次に、時間帯。これは潮汐と関連が深いと思うので何とも言えませんが、最初のうちは夜間でも
午後10時頃までの陽が沈んでから割と早目の時間帯で釣果が良く思えたんですが、午前0時を過ぎた
丑三つ時のような時間帯でも釣果はあったので、あまり決め付けない方がいいのかな? とも。
最後に、季節的な事。これはデータそのままで自分的には納得です。しかし何度も言いますが、
真冬に尺アジが釣れた事には驚愕しました。冬はメバルイメージだったので・・・
この時期の良型アジの接岸の理由は何なのか? 思い当たる節はいくつかありますが、正直、今でも
自分の中でハッキリした答えが得られてません。
残りの時期について、春~梅雨時期に掛けては産卵絡み、秋は食欲の秋かと。^^;
最後に総括的な事を書くと、秋は他の季節に較べて魚影が濃く、尚且つアジの食い気もMAX状態で
一番釣り易い時期に思えますので、ポイントの新規開拓なんかも他の季節よりも秋が一番結果に繋がる
感じがします。 で、大潮ならあまり潮位の高くない時間帯、それ以外なら潮の動く時間帯。
純粋に夜間のいつ頃というのはあまり気にせず釣れると思います。
まあ、書いてみれば結局ほぼアジングの定説通りではありましたが・・・;^^;; 以上です。
1/23 19:30 小潮 上げ5分
5/1 21:00 中潮 下げ4~5分
5/3 2:30 中潮 上げ3~5分
5/5 19:30 小潮 上げ6~7分
6/13 1:00 大潮 上げ2~3分
10/11 3:30 中潮 上げ2~5分
10/11 19:30 中潮 下げ2~3分
10/16 21:00 小潮 ほぼ満潮
10/23 23:15 大潮 ほぼ干潮
房総釣査に年間通して通ってみたのは、今回のようなデータを出してみて釣れる確率の高い時の条件が
何か絞られてくるのでは? と思っていたのですが・・・正直、日時・潮汐ともバラバラでした。
傾向としては諸般の定説通り潮が動いている時間帯で尚且つ上げ潮時が最も釣果が高い・・・ですが。
満潮干潮時のあまり潮の動きが感じられないような時間帯でも釣れてます。いや、むしろ・・・
これもあくまで私個人的経験による感覚になってしまいますが、満潮時よりもド干潮時、もしくは
その前後の潮位が低い時間帯の方が釣果が良いように感じてます。 推測なんですが、その場所に
アジが入ってきて捕食を繰り返してる間、釣り人が誰も入らず場荒れも無くアジが警戒心を解いて
ある程度長い時間その場所に留まっている・・・特に房総は元から水深が浅いので、人的プレッシャー
さえ無ければ尚更水深が浅くなる場所が捕食には好都合な訳で・・・。
ここでもう一度データを見返しつつ各釣行を思い返してみると、確かに大潮の満潮時とかのフル水位の
ような時は釣果が無く、またアジが釣れる気配も希薄だったような気がします。
次に、時間帯。これは潮汐と関連が深いと思うので何とも言えませんが、最初のうちは夜間でも
午後10時頃までの陽が沈んでから割と早目の時間帯で釣果が良く思えたんですが、午前0時を過ぎた
丑三つ時のような時間帯でも釣果はあったので、あまり決め付けない方がいいのかな? とも。
最後に、季節的な事。これはデータそのままで自分的には納得です。しかし何度も言いますが、
真冬に尺アジが釣れた事には驚愕しました。冬はメバルイメージだったので・・・
この時期の良型アジの接岸の理由は何なのか? 思い当たる節はいくつかありますが、正直、今でも
自分の中でハッキリした答えが得られてません。
残りの時期について、春~梅雨時期に掛けては産卵絡み、秋は食欲の秋かと。^^;
最後に総括的な事を書くと、秋は他の季節に較べて魚影が濃く、尚且つアジの食い気もMAX状態で
一番釣り易い時期に思えますので、ポイントの新規開拓なんかも他の季節よりも秋が一番結果に繋がる
感じがします。 で、大潮ならあまり潮位の高くない時間帯、それ以外なら潮の動く時間帯。
純粋に夜間のいつ頃というのはあまり気にせず釣れると思います。
まあ、書いてみれば結局ほぼアジングの定説通りではありましたが・・・;^^;; 以上です。
2010年11月12日
2010房総アジング総括②
アジングでの常夜灯の効果について。
今まで一番顕著だった例で、隣にカゴアジ師がいてその方は少し沖目のブレイクライン狙い。
かなり沖なので常夜灯の灯りの影響は全く無いと言っていいと思います。
しかもそのカゴ師、全くもって灯り云々を意識してる様子もありません。(そりゃそうか・・・?^^;)
私は手前の浅場の常夜灯の灯りが届く範囲&それより少し遠目を攻めてました。
カゴ師は仕掛けの都合上、当然手前の浅場(1〜2m弱程度)は狙えませんので必然的にそうなります。
最初、カゴのコマセに足止めされて手前の浅場にはアジが入って来ないだろうな〜と半ば諦めてました。
しかし、そんな状況でもヤツラ級の良型が釣れたんです。 今改めて検証してみると・・・
実はそのカゴ師の方、何度も同じ場所で同じ状況でご一緒してるんです。
お話した事は一度もありませんが・・・^^;
そしてパターンとしては、お互いポツポツ拾ってたり、どちらか一方がポツポツ釣ってるのにもう一方は
沈黙してたり、双方沈黙だったり・・・まあ、どれをとっても爆釣という事はありませんでしたが;^^;;
元々があまり大きな群れが回遊してくるような場所でもないと思うので、こういう形になったのかも。
で、それこそ正にアジの臨機応変なのではなかろうか・・・と。
前回記事に通じる事なんですが、同じ場所に回遊してくるアジの群れは毎回同じとも限りませんが
少なくとも釣り上げたアジの全てが金色の体色だったので、やはり近海定着型のアジかと。
で、上記の結果によりその時々によって、また、違う群れによって、更には群れの中でも個々に・・・
明らかに食事の対象を選り好みしてる様子が見て取れます。
何故かは・・・アジが人間の言葉で返答してくれれば越した事はないのですが(渇望笑)
とにかくここで言えるのは、コマセや付け餌に好反応な時もあれば、手前の常夜灯の灯りに寄った
ベイト類を食いたい時もある=アジングで釣れる=餌釣りにも勝る常夜灯の威力は確かに存在する、と。
もしこんなシチュエーションがあったら、諦めずに攻めてみるのも手ではないかと。
次に、常夜灯の色調について。
大部分を占めるのは白色灯・オレンジ灯・白熱球の三種類だと思います。
個人的にはオレンジ灯と白熱球が良い釣果を得られてます。白色灯の場合、アジが居るには居るん
だけど他の二つの色調の灯りよりも食いがシブい印象を受けるのは、気のせいでしょうか?
オレンジ灯&白熱球の灯りは白色灯より暗めで、更に明暗の境が曖昧な部分が多いような印象・・・
これは視力の良いアジからすればベイトから身を隠しつつも目視して狙える&逆に小さなベイトの視力
ではアジが見えにくいという、アジにとっては有利な捕食ゾーンが広く取れる、という事になるのでは。
あと、良型アジについては色調を問わず海面を照らす灯りが明る過ぎる場所は釣れる気配がしません。
活性の高い時はかなり明るい足元まで追ってきてヒットした事もありましたが・・・
どちらかというと、常夜灯自体の光量があまりなく全体的に薄暗く海面を照らしてる感じか、
常夜灯の光源自体はそれなりに強くても立地条件等含め海面を照らす光量自体がボンヤリした感じの
場所なら、かなり岸際にも寄ってくるような印象を受けます。
これはあくまで私個人の経験による感覚なので、参考程度に考えて下さい。
最後に、月が明るい夜の場合。
これは前回釣行時、夜にも関わらず良型アジがイワシ?等の小さなベイトを追って小規模ですが
目の前で何回かナブラが起こったのを目撃しました。
夜間に良型アジが小魚を追ってナブラを起こす・・・という事は、やはり普段よりは月灯りで周囲も
ある程度見えていて、且つベイトを追う事が出来る視界が得られているという事に他ならないかと。
その場所には常夜灯はあるにはあったんですが、正直その光量と月の光量では常夜灯効果はまるで
無効どころか月灯りが勝ってる勢いでした。これは逆に、アジが回遊して来そうで且つベイトを
追い詰めるのに好都合なポイントを押さえていれば、月灯りの夜でも常夜灯に頼らずこういった
シーンに遭遇する確率が高くなり、アジングが成立するのでは、と。
以前からそういったポイントを開拓したく考えてはいるんですが、やはり上記のような理由でついつい
釣れる場所に行ってしまい、まだまだ実地検分が足りない状態です。
新たに購入したリールがそんなようなネーミングなので、そのままに・・・とか。^^;
今まで一番顕著だった例で、隣にカゴアジ師がいてその方は少し沖目のブレイクライン狙い。
かなり沖なので常夜灯の灯りの影響は全く無いと言っていいと思います。
しかもそのカゴ師、全くもって灯り云々を意識してる様子もありません。(そりゃそうか・・・?^^;)
私は手前の浅場の常夜灯の灯りが届く範囲&それより少し遠目を攻めてました。
カゴ師は仕掛けの都合上、当然手前の浅場(1〜2m弱程度)は狙えませんので必然的にそうなります。
最初、カゴのコマセに足止めされて手前の浅場にはアジが入って来ないだろうな〜と半ば諦めてました。
しかし、そんな状況でもヤツラ級の良型が釣れたんです。 今改めて検証してみると・・・
実はそのカゴ師の方、何度も同じ場所で同じ状況でご一緒してるんです。
お話した事は一度もありませんが・・・^^;
そしてパターンとしては、お互いポツポツ拾ってたり、どちらか一方がポツポツ釣ってるのにもう一方は
沈黙してたり、双方沈黙だったり・・・まあ、どれをとっても爆釣という事はありませんでしたが;^^;;
元々があまり大きな群れが回遊してくるような場所でもないと思うので、こういう形になったのかも。
で、それこそ正にアジの臨機応変なのではなかろうか・・・と。
前回記事に通じる事なんですが、同じ場所に回遊してくるアジの群れは毎回同じとも限りませんが
少なくとも釣り上げたアジの全てが金色の体色だったので、やはり近海定着型のアジかと。
で、上記の結果によりその時々によって、また、違う群れによって、更には群れの中でも個々に・・・
明らかに食事の対象を選り好みしてる様子が見て取れます。
何故かは・・・アジが人間の言葉で返答してくれれば越した事はないのですが(渇望笑)
とにかくここで言えるのは、コマセや付け餌に好反応な時もあれば、手前の常夜灯の灯りに寄った
ベイト類を食いたい時もある=アジングで釣れる=餌釣りにも勝る常夜灯の威力は確かに存在する、と。
もしこんなシチュエーションがあったら、諦めずに攻めてみるのも手ではないかと。
次に、常夜灯の色調について。
大部分を占めるのは白色灯・オレンジ灯・白熱球の三種類だと思います。
個人的にはオレンジ灯と白熱球が良い釣果を得られてます。白色灯の場合、アジが居るには居るん
だけど他の二つの色調の灯りよりも食いがシブい印象を受けるのは、気のせいでしょうか?
オレンジ灯&白熱球の灯りは白色灯より暗めで、更に明暗の境が曖昧な部分が多いような印象・・・
これは視力の良いアジからすればベイトから身を隠しつつも目視して狙える&逆に小さなベイトの視力
ではアジが見えにくいという、アジにとっては有利な捕食ゾーンが広く取れる、という事になるのでは。
あと、良型アジについては色調を問わず海面を照らす灯りが明る過ぎる場所は釣れる気配がしません。
活性の高い時はかなり明るい足元まで追ってきてヒットした事もありましたが・・・
どちらかというと、常夜灯自体の光量があまりなく全体的に薄暗く海面を照らしてる感じか、
常夜灯の光源自体はそれなりに強くても立地条件等含め海面を照らす光量自体がボンヤリした感じの
場所なら、かなり岸際にも寄ってくるような印象を受けます。
これはあくまで私個人の経験による感覚なので、参考程度に考えて下さい。
最後に、月が明るい夜の場合。
これは前回釣行時、夜にも関わらず良型アジがイワシ?等の小さなベイトを追って小規模ですが
目の前で何回かナブラが起こったのを目撃しました。
夜間に良型アジが小魚を追ってナブラを起こす・・・という事は、やはり普段よりは月灯りで周囲も
ある程度見えていて、且つベイトを追う事が出来る視界が得られているという事に他ならないかと。
その場所には常夜灯はあるにはあったんですが、正直その光量と月の光量では常夜灯効果はまるで
無効どころか月灯りが勝ってる勢いでした。これは逆に、アジが回遊して来そうで且つベイトを
追い詰めるのに好都合なポイントを押さえていれば、月灯りの夜でも常夜灯に頼らずこういった
シーンに遭遇する確率が高くなり、アジングが成立するのでは、と。
以前からそういったポイントを開拓したく考えてはいるんですが、やはり上記のような理由でついつい
釣れる場所に行ってしまい、まだまだ実地検分が足りない状態です。
新たに購入したリールがそんなようなネーミングなので、そのままに・・・とか。^^;
2010年11月08日
2010房総アジング総括①
10月から良型アジが再び釣れ始め、現場で思った事や試してみた事を少し書いてみます。
遠目を探りたくてキャロではなく敢えて重めのジグヘッドを投入。
これは、良型のアジがこの重さのジグヘッドを果たして苦にする事なく食ってくるか? の検証。
正直言うと、ある程度の遠投が必要に感じた時でも夜間に複雑なキャロシステムを組んだり組み直す
よりは、届くのであれば多少重くとも単純にジグヘッドのみの方が釣り自体がやり易く、楽です。
また、房総の海は他場所と比較して全体的に浅い事もジグヘッド単体で可能と思える理由の一つです。
使用したのはカルティバクロスヘッド4g。太軸&針もデカくてヤツラ級の抜き上げも問題無し。しかし・・・
さすがに4g、ちと重過ぎるか? と思いきや! 食い気のある良型アジには、全く関係ありませんでした。
よく釣り雑誌の記事で大型ほど小さいアタリとか繊細な吸い込みバイトを捉える・・・など目にしますが。
これまで約一年に渡る房総釣査の中で良型アジに限定したアタリを思い返すと、少なくとも私が釣った
アジに関してはほぼ全て突然ドスッときてリーリングの手を止めるような重々しくて明確なアタリでした。
これはその時々のアジの活性などにも関係すると思いますが、よくよく考えてみれば誘い方は違うかも
しれませんが5gのもっとボリュームのあるプラグに食ってきたり10g以上のメタルジグにバイトしてくる
アジもいる訳ですから、当然といえば当然かもしれません。
更に今まで釣った良型アジのヒットパターンは、全てリトリーブです。
最初にリトリーブで一尾目がヒット。が、少しの間アタリが消えたりする事、ありますよね?
しかし、数は少なくともある程度型の揃った小さな群れがそこに居る事は、気配で・・・判るんです。
で、試しに縦に誘ってみるんですよ。 しかし正直、縦に誘って食ってきたためしがありません。
私の腕もあると思いますが・・・^^; しかしどうも、ルアーは認識してるのに食わない雰囲気を感じます。
縦に誘うと逆に警戒するのか? それとも、違和感を感じて追わなくなるのか? ・・・活きた魚食嗜好?
暫くしてまたリトリーブに切り替えるとヒットします。
少し前までのジンタサイズ~中型サイズのアジは、リトリーブにも反応して食ってきますが、
それよりむしろリフト&フォールの縦の誘いによく反応して食わせやすい印象を受けました。
以前から思っていたんですが、このハッキリしたヒットパターンの差は、一体何なのか?と。
これについて、実は少し前から薄々思う所あったんです。 ・・・あくまで推測ですが。
アジの種類。同じマアジでも、居着きと回遊型。これは以前も述べてみたんですが・・・
よく、居着きアジはリトリーブに、回遊型はリフト&フォールに好反応を示すと。
・・・しかし私が感じているのは、地域によっての違いもあると思いますが房総で釣れるアジに関しては
ヒットパターンによるアジの種類の区分けというよりも、同じ種類のアジが体格差・その時の標的の
違い・海況などにより、臨機応変に対応している違いによる差なのでは? と。
釣ったアジをよく見ると、体の大小問わずほぼ全て地着きアジの特徴である金色の体色をしてます。
これは光の当たり具合でそう見える・・・なども考えられますが、それを差し引いてもやはり同じ近海の
浅棚域に生息するアジの特徴をはっきりカラダで(笑) 示しています。
釣った場所の違いはあれど、日本全国的に見ればほぼ同地域で釣れたものと言えますし、更に言えば
逆にそんな限られた地域のしかも陸寄りの浅い海域に大きく異なる種類のマアジが高い比率で常に
混在するとも考えにくいと思うんです。
これらを総合して考えると・・・私的見解では、
房総での陸っぱりアジングで釣れるアジは以前述べた同種であって異種交配型も含めて、
ほぼ全て地域定着型のマアジなのでは? と。
しかも、かなり近隣地域密着型と思えます。密着型とはいっても勿論回遊はしますよね。魚なので(泳笑)
そこなんです。相手の実情が解れば、その地域での季節&年間を通した動き・回遊ルート・餌場など。
次のステップというか、ポイントの選択肢も増えるしより実のあるアジングになるかと。
ここら辺は、房総に長年通ってる釣り人ならある程度感覚的に掴めてるものと思うんです。
その領域に達するには、まだまだ・・・永いですね。 σ(^^;
遠目を探りたくてキャロではなく敢えて重めのジグヘッドを投入。
これは、良型のアジがこの重さのジグヘッドを果たして苦にする事なく食ってくるか? の検証。
正直言うと、ある程度の遠投が必要に感じた時でも夜間に複雑なキャロシステムを組んだり組み直す
よりは、届くのであれば多少重くとも単純にジグヘッドのみの方が釣り自体がやり易く、楽です。
また、房総の海は他場所と比較して全体的に浅い事もジグヘッド単体で可能と思える理由の一つです。
使用したのはカルティバクロスヘッド4g。太軸&針もデカくてヤツラ級の抜き上げも問題無し。しかし・・・
さすがに4g、ちと重過ぎるか? と思いきや! 食い気のある良型アジには、全く関係ありませんでした。
よく釣り雑誌の記事で大型ほど小さいアタリとか繊細な吸い込みバイトを捉える・・・など目にしますが。
これまで約一年に渡る房総釣査の中で良型アジに限定したアタリを思い返すと、少なくとも私が釣った
アジに関してはほぼ全て突然ドスッときてリーリングの手を止めるような重々しくて明確なアタリでした。
これはその時々のアジの活性などにも関係すると思いますが、よくよく考えてみれば誘い方は違うかも
しれませんが5gのもっとボリュームのあるプラグに食ってきたり10g以上のメタルジグにバイトしてくる
アジもいる訳ですから、当然といえば当然かもしれません。
更に今まで釣った良型アジのヒットパターンは、全てリトリーブです。
最初にリトリーブで一尾目がヒット。が、少しの間アタリが消えたりする事、ありますよね?
しかし、数は少なくともある程度型の揃った小さな群れがそこに居る事は、気配で・・・判るんです。
で、試しに縦に誘ってみるんですよ。 しかし正直、縦に誘って食ってきたためしがありません。
私の腕もあると思いますが・・・^^; しかしどうも、ルアーは認識してるのに食わない雰囲気を感じます。
縦に誘うと逆に警戒するのか? それとも、違和感を感じて追わなくなるのか? ・・・活きた魚食嗜好?
暫くしてまたリトリーブに切り替えるとヒットします。
少し前までのジンタサイズ~中型サイズのアジは、リトリーブにも反応して食ってきますが、
それよりむしろリフト&フォールの縦の誘いによく反応して食わせやすい印象を受けました。
以前から思っていたんですが、このハッキリしたヒットパターンの差は、一体何なのか?と。
これについて、実は少し前から薄々思う所あったんです。 ・・・あくまで推測ですが。
アジの種類。同じマアジでも、居着きと回遊型。これは以前も述べてみたんですが・・・
よく、居着きアジはリトリーブに、回遊型はリフト&フォールに好反応を示すと。
・・・しかし私が感じているのは、地域によっての違いもあると思いますが房総で釣れるアジに関しては
ヒットパターンによるアジの種類の区分けというよりも、同じ種類のアジが体格差・その時の標的の
違い・海況などにより、臨機応変に対応している違いによる差なのでは? と。
釣ったアジをよく見ると、体の大小問わずほぼ全て地着きアジの特徴である金色の体色をしてます。
これは光の当たり具合でそう見える・・・なども考えられますが、それを差し引いてもやはり同じ近海の
浅棚域に生息するアジの特徴をはっきりカラダで(笑) 示しています。
釣った場所の違いはあれど、日本全国的に見ればほぼ同地域で釣れたものと言えますし、更に言えば
逆にそんな限られた地域のしかも陸寄りの浅い海域に大きく異なる種類のマアジが高い比率で常に
混在するとも考えにくいと思うんです。
これらを総合して考えると・・・私的見解では、
房総での陸っぱりアジングで釣れるアジは以前述べた同種であって異種交配型も含めて、
ほぼ全て地域定着型のマアジなのでは? と。
しかも、かなり近隣地域密着型と思えます。密着型とはいっても勿論回遊はしますよね。魚なので(泳笑)
そこなんです。相手の実情が解れば、その地域での季節&年間を通した動き・回遊ルート・餌場など。
次のステップというか、ポイントの選択肢も増えるしより実のあるアジングになるかと。
ここら辺は、房総に長年通ってる釣り人ならある程度感覚的に掴めてるものと思うんです。
その領域に達するには、まだまだ・・・永いですね。 σ(^^;